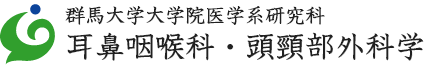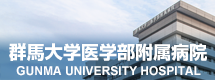こんにちは。松山です。
IRS(世界鼻科学会)&ISIAN&ERS2025に参加してきました。
開催都市は東欧、ブダペスト(ハンガリー)。
日本からの直行便はないため、ヘルシンキ(フィンランド)経由で向かいました。
実は私、出発前は「ハンガリーって行っても見るところあるの?」なんて言っていたんですが…
まず伝えたいのはこれです。
『ブダペストの街並みは美しい!!』
ドナウ河周辺の景観は世界遺産にも登録されていて、国会議事堂やドナウ河にかかる「くさり橋」などの建造物の美しさは、歴史を感じるとともに、まさに魅了されます。
ブダペスト全体でも、日本のようなタワマンや高いビル群は一つもありません。歴史的な街並みを、大切に残していて非常に風情があります。電光広告などもなく、落ち着いた照明の温かみある雰囲気にはなんともいえない情緒がありました。
今回の機会がなければ、人生で絶対行くことがなかったブダペストですが、本当に行ってよかったと思いました。ぜひ一度訪れてみてほしいです。
さて、学会の話を。
※↑今回、群大からは私一人の参加でしたが、埼玉医科大学の細川悠先生と一緒に行ってきました。埼玉医科大学からはなんと専攻医1年目の小林先生も参加されていました。4月に耳鼻咽喉科医になったばかりなので、研修医時代に演題を提出していたということ。すごいモチベーションです。
今回はERS(欧州鼻科学会)も共同開催ということもあり、参加人数は東京開催やシカゴ開催より多かった気がします。頭蓋底、2型炎症、病態生理、嗅覚、鼻形成、悪性腫瘍などなど多彩で魅力的なセッションが行われていました。会場にCadaverが持ち込まれ、目の前でスペシャリストの手術手技をみることができるCadaver Dissection(ご献体による解剖デモ)は、さすが国際学会です。
最近のトレンドとしてRhinoplasty(鼻形成)の話題が多くなっている印象を受けました。外鼻形成や鼻中隔前弯手術は今後広く必要な手術になってきそうです。またENS (Empty Nose Syndrome)が一つのシンポジウムになるなど注目度が高まっていました。ENSは鼻本来の加湿機能や鼻腔抵抗感が失われ、鼻腔が乾いたり、鼻閉感が生じる状態です。
ESSが主流となり、下鼻甲介を大きく切除してしまうコンコトミーやズブコンと呼ばれる粘膜下下鼻甲介骨切除をやりすぎ、鼻腔空間の異常拡大がENSの原因とされています。
鼻の中は広いのに、「鼻が詰まってる感じがする」って人に会ったことありませんか?
それ、ENSの可能性があるんです。
2型炎症の嗅覚改善手術でもそうですが、医療者側による長期的な合併症を作ってしまわないように、鼻が本来持つ生理機能を損なわない手術設計がますます重要であると実感しました。
※↑日本からも多くの先生方が参加されていて、現地ではたくさんの交流の機会がありました。また、ベルギーの耳鼻科医の先生と夕食をご一緒する機会もあり、国際的な耳鼻科事情についての話もできて、非常に刺激的な時間でした。
最後に、
ハンガリーはハンガリーオーストリア帝国から、第一次世界大戦、第二次世界大戦、その後のソビエト連邦による共産主義支配と続き、1989年、東西冷戦の終結とともに民主化。2004年にEUに加盟し、現在があります。歴史的に周辺諸国に翻弄され続け、ようやく最近になって安定的で平和な暮らしを確保した国です。
第二次世界大戦末期、ハンガリーでもナチス下による多くのユダヤ人虐殺がドナウ川岸で行われました。犠牲者は川に突き落とされる前に、靴を脱がされてから処刑されたそうです。(当時の靴は貴重な物資だったため、再利用目的で奪われた) 子供の靴もありました。
ハンガリーでは、美しい街並みが残っている反面、過去のホロコーストや共産主義での拷問弾圧など、過去の悲しい記憶を風化させないための建造物がいくつも見られました。
ブダペストを歩くと、今の自由や平和が「当たり前ではない」と気づかされます。
日本人としても、群馬大学人としても、若い世代に、楽しいことだけでなく──
二度と繰り返してはいけない、目をそむけたくなるような悲しく痛ましい歴史の教育も大事だなと、改めて思うのでした。
最後は少し湿っぽくなってごめん。
2026年はバンコク(タイ)、2027年はセビリア(スペイン)で開催されます。
来年も参加できるように日々の診療、研究をまた頑張っていこうと思います。
多くの人が国際鼻科学会に一緒に参加してくれることを願っています。
本出張を支援してくださった医局の皆様、同門会の皆様にこの場を借りて御礼申し上げます。
松山敏之